2024.01.22(月)
町内会の行事
[ システム開発部 ]
お疲れ様です。システム開発部の黒澤です。
寒い日がまだまだ続くと思いきや、突然暖かくなったりと、地域にもよりますが寒暖差が大きいので身体には十分お気をつけくださいませ。
話は変わりますが皆様は地域の町内会・自治会等、地域によってさまざまな呼び方があると思いますが催しものや行事などは存在しますでしょうか?
夏祭りや運動会、球技大会などはよく耳にしますが私の町内会の行事は少し違います。
流鏑馬(やぶさめ)です。

馬です。ヒヒーンです。
私、半年程前に博多駅東ビルから電車で30分程度の人口密度:低、平均年齢:高、街灯:少、駅の改札:無、の地域に引っ越したのですが、以前住んでいた地域の催し物とはあまりにも差があったので紹介させて頂きます。
毎年9月に近所の神社で開催されるお祭りの中の1イベントがこの流鏑馬(やぶさめ)で、疾走する馬に乗りながら鏑矢(かぶらや)で的(まと)を射る、儀式のような教科書でみるあれです。
遠方からも大勢の方が見に来るようですが、私は開催する側なので準備に参加させて頂きました。
細かい所で言うと、的(まと)の準備やお馬さんが走る区画整備などです。
また、神社で開催されるお祭りのため、鳥居に掛けるしめ縄を一から手作りで編み込みます。
このしめ縄作りはお祭りの1ヶ月前から準備が始まり、藁選り(わらすぐり)から始まります。
「藁選り(わらすぐり)」とは、刈りとられた稲を選(すぐ)り、稲の茎以外の部分を省き、きれいな茎だけを選ぶことで、この選別した藁で、鳥居に飾る巨大しめ縄をつくります。
私も見よう見まねで稲を選(すぐ)りましたがなかなか難しく、邪魔だけはしないように注意して作業しました。この巨大しめ縄は、選別した藁100束ほどの集合体【A】を長さ5mになるまで連結したもの【B】を3本作り、この3本の【B】を三つ編みにすると巨大しめ縄となるという合体ロボのような構造になっています。
完成した巨大しめ縄を神社の鳥居に飾る時の話ですが、鳥居の両端に「竹」を立て掛けて、巨大しめ縄を外れないようしっかりと固定します。
そこでとある先生から「ようきびっちょって!おとこん結びで、はずれんごと!」と。
倒置法を使った言い回しであることは理解したのですが、何を指示されたのか分からずにいると、どうやら、きびっちょって(≒きびりなさい)、きびるというのは福岡の方言で「結ぶ」という意味で、要約すると(鳥居に立て掛ける竹を)鳥居と外れないように男結びでよく結んでおくよう指示をされたのです。
この男結びが初耳で、その場で教えてもらうも、なかなか理解できません。
ただ、しめ縄以外の準備でも、至る所で登場するこの「きびる」行為は男結びが必須です。
40過ぎの大人が、ことあるごとに「ねぇー、結んでー」とは言えません...
男結びを覚えないと一人分の仕事が出来ないため、新参者の私はきびる用の紐の端切れを頂戴し自宅で感覚で習得できるよう猛特訓。
ある程度結び方を覚えても、しっかりときびることが出来ず、色々な物で試しています。
先日、妻を近くのイチョウの木にきびろうとしたのですが、何かを察したのか、頑なに拒否されました...
是非とも皆様に見せたかったです。でもまだチャンスはあると思っているのでご期待ください!
と、初めてのお祭りはきびり方を習得しただけで終わりましたが、とても貴重な体験をさせてもらいました。
もしかすると、流鏑馬は無くても、以前住んでいたところでも探っていないだけで、面白い行事がたくさんあったのかもしれません。
皆様の経験談も是非とも聞かせてください。
以上、高級賃貸保証のフォーシーズシステム開発部黒澤 のフォーシーズブログでした。
毎日の記事は下記リンクから閲覧できます。
システム開発部の記事は下記リンクから閲覧できます。
|

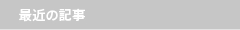



|

